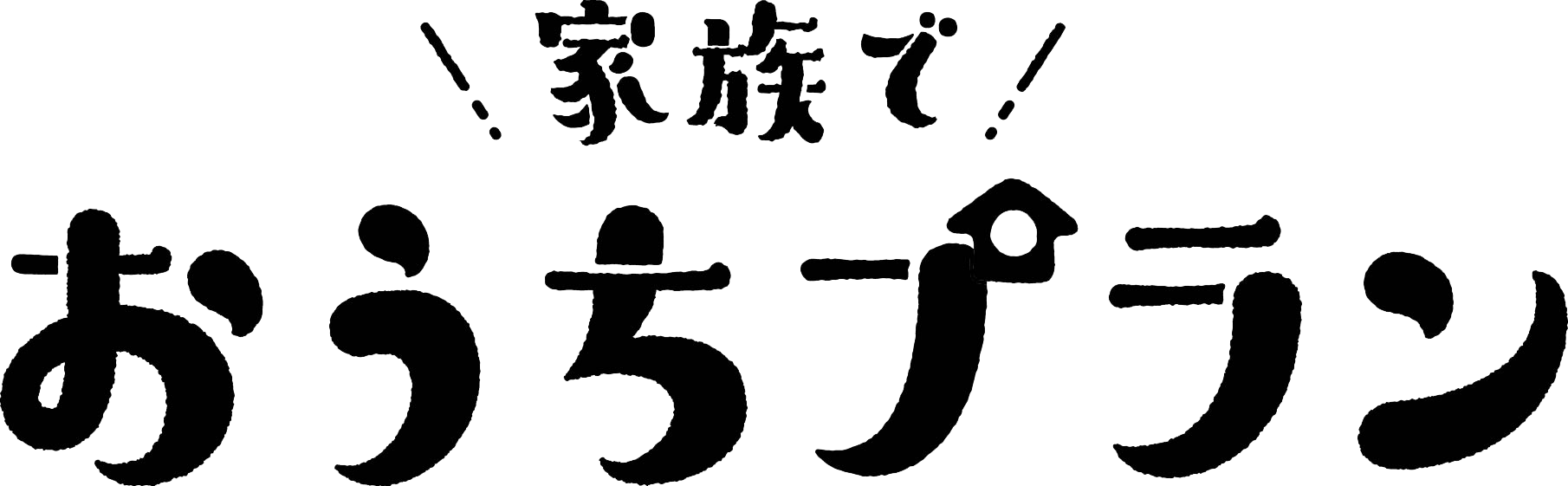家づくりを始める前に知っておきたい用語集


あ行
■RC造(あーるしーぞう)
鉄筋コンクリートreinforced concrete 構造の略。
コンクリートと鉄筋を組み合わせた構造材料である鉄筋コンクリートを使用して柱や梁(はり)、床などを造ること。耐震、耐火、耐久性に優れた最も一般的な不燃建築。
■アイランドキッチン
流し台や調理台を壁から離し、独立した島のようにする配置法。
大人数で料理を楽しめて、LDKの中に視線を遮るものがなくなるのでホームパーティーを開く家庭などで人気がある。
■上がり框(あがりかまち)
玄関の土間から床への上がり口に設ける化粧の横木材。
最近は建て替え時に前の住まいに使用していた愛着のある上がり框を、新しい住まいに再生して使うこともよく見かける。
■アプローチ
門から玄関までの通路。
道路からいきなりではなく、植栽や曲がった通路などを通って玄関に入ることにより、威圧感なくプライバシーを守るなどの機能や、空間イメージをつくることができる。

■イニシャルコスト
住宅設備などの当初の購入にかかる費用。
これに対し、維持にかかる費用をランニングコストという。
■ウォークインクローゼット
大型収納空間で、人が歩いて入れるくらいの広さがあることからこう呼ばれる。
主に衣類などの収納スペースとして、寝室などに隣接して設けられることが多い。

■ウォールナット
クルミ科クルミ属の広葉樹。
一般にクルミ属の樹種は、材質が優れ、加工性が良く、狂いが少なく、比重が軽い割に強度が高い素材のため、建築用造作材や家具、楽器、彫刻などに幅広く用いられている。
■エコキュート
大気中から熱を吸収し、その熱を利用してお湯を沸かす給湯システム。
正式名称は自然冷媒ヒートポンプ給湯器。燃焼しないので排気がなくクリーン。エネルギー効率が高い。
■エコ(エコロジー)塗料
健康や環境に配慮した塗料。原料に石油化学系でなく植物油を使用。
日本古来のニカワや柿渋、蜜蠟(みつろう)も該当する。
■S造(えすぞう)
主要部分に鉄骨(steel)を用いた構造でS造と呼ばれている。
建物の柱や梁などの主要な部分に組み立てられ、主に高層建築に用いられる。
■横架材(おうかざい)
木造軸組み工法やラーメン工法構造などで、梁や桁、棟木など水平方向に架け渡す構造材のこと。
■オーク
アメリカ産の樫(カシ)材や楢(ナラ)材で、木の色が白いものはホワイトオーク、赤いものはレッドオークと呼ぶが、日本では単にオークという。
■オープンキッチン
リビングやダイニングと同じ空間にあるキッチン。室内をワンルームとして広く使う開放的な間取りによく使われる。
以前は、キッチンはなるべくリビングなどの家族や来客が集う場所から見えにくい位置に配置していたが、今ではキッチンを中心にして、家族の顔が見え、料理をしながら会話も交わされるオープンキッチンの人気が高くなってきた。

か行
■開口部
通行や眺望、採光、換気、通風を目的として設けられた部分の総称。主に窓や出入り口のことをいう。
■外構工事
敷地内の門や塀、アプローチ、ガレージ、庭など建物以外の工事。
■瑕疵担保履行法(かしたんぽりこうほう)
瑕疵とは欠陥やキズを表す法律用語。新築住宅に構造上主要な部分や雨水を防止する部分に何らかの欠陥があった場合、この法律により買い主は売り主に対して十年間の瑕疵担保責任を追及できる。
売り主は瑕疵の補修などが確実に行われるように保険加入、または供託が義務付けられ、売り主が倒産した場合も、瑕疵補修に必要な金額が保証される。
■壁構造
壁によって躯体(くたい)を支える構造。柱や梁という部材ではなく、柱と壁を一体化して造る。床板と壁板が線の部分で接合される構造のため、軸組み構造と比較して耐力が大きい。
■可変住宅
家族構成やライフスタイルの変化に対応して室内空間を組み替えられるように、あらかじめ計画された住宅。
高齢になり体が不自由になっても生活しやすいよう、あらかじめ配慮しておくことを「加齢配慮」といい、これによって将来のリフォームコストを抑えることもできる。
居住部分に柱や耐力壁などを入れず、間取りを自在に組み替えられるようにすることを「スケルトン・インフィル」といい、マンションや一部の木造建築でも採用されている。
■ガルバリウム鋼板
鋼板にアルミニウムと亜鉛の合金を溶融メッキしたもので、耐食性に優れ、屋根、外壁、ダクトなどに使われている。
■完成保証
工事途中で万一、請負業者が倒産した場合に、代わりの業者がその工事を引き継いで完成させる制度。
請負業者が完成保証の登録事業者でなければ受けられず、また保証機関によって保証内容が異なるので注意が必要。
■基礎
基礎は、建物の壁に沿って連続して造られる鉄筋コンクリートの基礎。木造などを中心にして最も一般的に用いられる。
ベタ基礎は、建物の底をコンクリートで覆う方法。接地面積が増えることで荷重が軽減するため、地盤の弱い土地で用いられることが多い。
杭(くい)基礎は、固い地盤に達するまで杭を打ち、建築物を支える方法で、軟弱な地盤などで用いられる。
■躯体(くたい)
建物の構造体のこと。柱・梁・床・壁などの部分の総称。
■グラスウール
ガラスを溶接して作った繊維状の断熱材。
ガラス繊維の間に空気が大量に含まれており、保温性や吸音性が高い。
■珪藻土(けいそうど)
植物性プランクトンが化石化してできた土。
珪藻土の壁は湿度を調節する性質があり、結露しにくいという特徴がある。そのほか消臭や断熱、防音などの効果もあり、天然素材として人気がある。
■結露
住宅に生じる結露には、ガラス表面など低温部分に触れてできる表面結露と、壁内部にできる壁体内結露がある。
表面結露はカビの発生を促し、アレルギーの原因となる。
目に見えない壁体内結露は、建物を内部から腐らせてしまう。建築の際には、壁の構造を考えて、通気層をつくったり防湿シートを張ったりするなど処置が必要となる。
■玄昌石(げんしょうせき)
粘板岩(スレート)。玄関や浴室の床などに使われる黒、または青系統の天然石。
■建築条件付き宅地
売買に関して、特定の業者との工事請負契約が条件となっている宅地。プランニングに関しての条件ではない。
■建ぺい率(容積率・斜線制限)
建築面積の敷地面積に対する割合。
建築基準法では、保安や衛生、環境保全上で必要な空き地を確保するため、さまざまな制限がある。
建物の外壁(または柱の中心線)で囲まれた面積を建築面積といい、建ぺい率は用途地域ごとに割合が決められている。
容積率は、床面積を合計した延べ床面積の敷地面積に対する割合。用途地域ごとに割合が決められている。
斜線制限は、建物の高さに対する制限で、①道路斜線制限 ②隣地斜線制限 ③北側斜線制限の三つがある。
屋根の形や傾斜など、外観デザインの制約を受けることがある。
■工事費用
建築にかかるすべての費用の合計(土地代別)を総工費、建物本体にかかる費用を本体(建築)工事費という。
このほか、地盤改良や浄化槽設置など土地の条件によってかかる付帯工事費、車庫やアプローチなどの外構工事費、配管を敷地内まで引き込む屋外設備工事費、空調設備工事費や照明器具費などさまざまな工事費があり、メーカーごとに区分や名称、見積もりの仕方が異なるため、どの工事費にどこまでの工事が含まれるのか確認が必要だ。
また、契約後に発生した設備にかかるものを別途工事費といい、追加見積もりを出してもらえる。
■構造計算
地震や風などの力に対し、躯体がどの程度耐えられるかを数値化すること。
一定規模以上の建築物には、建築確認申請時に「構造計算書」の提出が義務付けられている。
個人のための一般的な住宅(二階建てまで)には、提出の必要はない。
構造計算は建築士が行うが、専門知識と高価なソフトウエアが必要なため意匠設計とは分業されているケースが多い。
■腰壁(腰板)
下半分に板材を張った壁。インテリアとして取り入れる場合も多いが、本来は床から腰の辺りの壁が汚れやすいため、交換が容易な木の板を使用したもの。
■小屋裏
屋根裏に当たる空間。通常は天井で室内と分けるが、家全体の断熱・気密性能の向上に伴い、最近はオープンにして居室やロフトに使うことも多い。
さ行
■サーキュレーター
空気を循環させる装置。
冬には、室内の上部にたまる暖かい空気を下部へ循環させ、夏には足元にたまる冷たい空気を上部に循環させ、室温を均一にする効果がある。
天井に付けられるシーリングファンなどが代表的なもの。
■サイディング
外装材の総称。セメント系、セラミック系、金属系などの素材がある。
従来の外壁仕上げの定番だったモルタル吹き付け、塗り壁などと比べ耐用年数が長くメンテナンスの必要も少ないため多くの住宅で採用されるようになっている。
カラフルで人気の高いガルバリウム鋼板も金属系サイディングの一つ。素材の質感やカラーバリエーション、断熱、耐火、防水、防汚などの表面加工などさまざまなサイディングが開発されているため、素材による特徴は一概には言えなくなってきている。
■サッシ
窓枠がプラスチック製の樹脂製サッシは、アルミサッシに比べて熱が伝わりにくく、断熱性に優れ、結露も生じにくい。
木製サッシも同様に、断熱性能が高い。
複合サッシは外部をアルミ製にして強度や耐久性を高め、内部を木製や樹脂製にして断熱効果を高めている。
ブラインド内蔵サッシは、二枚のガラスの間に内蔵したスリムなブラインドを開閉したり角度を調節したりでき、遮音性や遮光性に優れている。
■サニタリー
キッチンを除く浴室、洗面所、トイレなどの水回りの総称。
一室にまとめた場合、その空間をサニタリールームと呼ぶこともある。サニタリー(sanitary)の意味は「清潔な、衛生的な」。
■天井扇
室内の空気を循環させるために天井に取り付けられた回転する羽根。
羽根を回転させることで空気を循環させ、室内の上下の温度差を均一にする働きがある。
■軸組み
木造住宅を構成する骨組みの中で、屋根を支え、壁を構成する骨組みをいう。
主なものには土台、通し柱、梁などがある。
これらを主な構造体とする工法を木造軸組み工法という。
■漆喰(しっくい)
消石灰にわらや麻などの植物繊維、砂、のりを混ぜて水で練ったもの。
昔から民家などの外壁仕上げに使われてきたが、水や湿気に弱い性質がネックとなった。
近年では、天然素材の「呼吸をする壁」として見直され、内壁に使用する住宅も増えている。
■シックハウス症候群
目の痛み、頭痛や吐き気、体調不良など、建築に使われている建材や接着剤、仕上げ材から放出される化学物質が原因で起こる症状のこと。
原因としてホルムアルデヒドや有機リンなどの揮発性有機化合物が指摘されている。
近年ではシックハウス対策が進み、自然素材や低濃度建材の選択、通風や換気を考慮して設計することで、ある程度コントロールできる。
■指標
住宅に関するさまざまな性能を客観的に評価する数値。
N値は、地盤の固さを示す。63.5㎏の重りを付けた鋼鉄棒を75.0㎝の高さから自由落下させ、30.0㎝打ち込むのに必要な回数。数値が大きいほど地盤が固い。
C値は、延べ床面積当たりの隙間面積。測定は実際に建てられた建物で気密測定によって算出される。数値がゼロに近いほど気密性が高い。
Q値は、熱損失係数。建物内と外気の差を一度としたとき、外に逃げる時間当たりの熱量を床面積で割ったもの。数値がゼロに近いほど断熱性が高い。
L値は、遮音性能。上階で発生させた音を下階で測定して算出する。特にマンションなどでは遮音性能は重要な指標。数値が小さいほど遮音性能が高い。
■集成材
完全に乾燥させた木材を集成して角材や板材にしたもの。
表面に杉やヒノキを張るなどして整え、柱や敷居、かもいなど、大抵のものをつくることができる。
見た目が美しく狂いがなく、良材が少なくなっている現在、ますます使われる傾向がある。
■住宅性能表示制度
住宅品確法の中で定められたもの。
住宅の性能を施工先ではなく、第三者機関から審査・評価してもらい、その情報を住宅取得者に提供する。
これによって、性能評価の高い住まいは資産価値が高まる。構造の安定や光や音の環境、防犯など10分野に分かれている。
■真壁(しんかべ)
日本の伝統的な木造建築による壁。
構造材の柱をそのまま見せる造り。対して、板張りや壁塗りで柱を外部に現さないようにした壁を、大壁という。
■スキップフロア
一部屋の中で段差を設けてつくった空間や、中二階のように意図的に床の高さを半階段ずらしてつくった空間。
■筋交(すじか)い
在来工法で柱と柱の間に斜めに渡す補強材のこと。
台風や地震など横から建物にかかる力に耐え、変形を防ぐ。
建物全体を強固にするために必ず入れるものであり、釣り合いよく配置してねじれを生じさせないように入れる。
■ストリップ階段
蹴込板(けこみいた)がなく、骨組みがむき出しになった階段のことで、スケルトン階段ともいう。
■スマートハウス
電力やガス、水道などの家庭のエネルギー使用量をリアルタイムで把握することができるシステム(HEMS「Home Energ y Management System」)をはじめとしたエネルギー関連設備を標準装備した住宅をいう。
アメリカで誕生した言葉「Smart House」をそのまま日本語にしたもので、日本ではHEMS を導入していることが最低条件。エネルギーが見えるので、節電が期待される。
■接道義務
建築基準法で定められた敷地が道路に接する幅。2mなければならない。
■セルロースファイバー
新聞紙古紙をリサイクル生産した断熱材。調湿、防音効果や、安全性、防火性が認められている環境配慮型断熱材。
た行
■耐震構造
筋交い、補強金物などで地震などの揺れに対する強化を行うこと。
一方、免震構造はバネやローラー、緩衝材などをかませることによって揺れを逃がすことを指す。
■耐力壁
強度を有する壁のこと。
パネル工法の壁パネルや枠組み工法の壁部分、木造軸組みの在来工法では筋交いの入った壁などをいう。
■建具
戸や扉、ふすま、障子などの総称。
建具の良しあしが住まいの機能を決定するといわれている。
■断熱
断熱とは、住宅や建物の中への熱の伝わりを抑えることです。室内の温度は、外気温の影響を受ける。断熱性が低い住宅は夏は暑く冬は寒い状況となるため、冷暖房器具をフル稼働しなければ快適性が著しく低下する場合もある。
一方、断熱性が高い住宅は夏は室内を涼しく保ち、冬は暖かさを守ることができるため、快適な環境を実現できる。また、部屋と部屋の温度差も小さくなるため、ヒートショックのリスクを抑えることも可能。
■ダンパー
吸排気、燃焼ガスや煙などの通路を開閉し、抑制する扉をいう。
ガスや石油の燃焼には空気が必要だが、空気の流入量を制御し、適切な燃焼をさせるために使われる。
■長期優良住宅に対する税の特例
長期優良住宅とは劣化対策、耐震性、維持管理、更新の容易性、バリアフリー性、省エネルギー性、住戸面積、住居環境、維持保全の方法など、さまざまな認定条件を満たした住宅をいう。
長期優良住宅に認定されると不動産取得税や固定資産税の軽減など税制上の優遇措置やローンの優遇措置が受けられる。
居住年によって控除対象額や控除額に変更があるので確認が必要。
■坪単価
施工費用を延べ床面積で割り、ひと坪当たりの単価を出したもの。
一般的に建築費の目安として使われているが、同じ住宅設備を持つ物件で、坪数が大きければ、坪単価が安くなるので、価格を比較する上での参考にはならないことに注意。
な行
■納戸
図面にこう表記されている場合、建築基準法の採光、通風などの基準を満たせず「居室」にできない部屋であるケースがほとんど。
ほかに「サービスルーム」などと表記される場合もある。
■24時間換気システム
室内の空気を新鮮に保つために、機械などで計画的に換気するシステム。
住宅の高気密化、高断熱化に伴い、2003年から新築住宅に設置が義務付けられている。
近年は冷暖房のエネルギーを逃さない、熱交換式換気扇が普及しており、その機能も高まっている。
■根太(ねだ)
コンクリート基礎と床板の間に横に渡した木材。
床板を支えるのが目的で、床鳴りの原因の一つはこの取り付け方法と材質による。
■軒、ひさし
軒は外壁より外側に出た屋根部分。
ひさしは窓やテラスなどの上部外壁に付ける片流れの屋根状のもの。どちらも外壁や開口部に雨風や直射日光が当たるのを防ぐ働きをする。
■延べ床面積
一階、二階、地下、収納スペース、バス、トイレなどを合計したスペースをいう。
条件によってはロフトや地下などは換算されないこともある。
は行
■パース
一定の図法により建物の内観や外観を立体的に描いた透視図(perspective)。
コンピューターによる精密なものや、視点を移動させたものなども描けるようになってきている。
■バルコニー
バルコニーやベランダ、テラスなどは、いずれも住宅から突き出た空間をいう。
日本では、バルコニーは二階以上、ベランダは各階でひさしの付いたもの、テラスは一階と一応区別される。
■パントリー
食料品や食器などを収めておく食料庫のこと。
■引き込み戸
壁の中に戸を引き込む(収納する)ことができる戸のこと。
リビングと和室を一体の空間としながら、引き込み戸を設けることで、間仕切りできるようにする。
■ビニールクロス
塩化ビニール製の壁紙をいう。
クロスは織物、布地という意味だが、織物風の布目が印刷されていなくても、壁紙を一般にクロスということもある。
■標準仕様
新築の戸建て住宅やマンションなどに設定されている設備機器や内装、外装など、共通して適用される仕様のこと。
「坪単価」はこの標準仕様を基に算出されることが多い。
■ppm
parts per million の略で百万分の一のこと。
建築では主に有害物質量の測定などに用いる。
■複層ガラス
ペアガラス、トリプルガラスなど二重、三重にしたガラスに空気層を挟んで組み立てたもの。
断熱性を高めるためにアルゴンガスを注入したり、真空にしたりした複層ガラスもある。
■不同沈下
建物を支えられず地盤が沈下していく状態。
これによる建物の傾きは新築住宅のいわゆる「10年保証」の対象。
■フラット35
長期固定金利住宅ローン。資金の受け取り時の金利と返済額が一定なので、長期の返済計画が立てやすい。
優良住宅に対する優遇措置として金利が一定期間減少する「フラット35S」もある。
■補強金物
木と木など、部材同士の接合部分の強度を高めるために用いる金属製金具。
耐震基準クリアのために使われる。「筋交いプレート」や、基礎と土台を結ぶ「アンカーボルト」などがある。
ま行
■窓の種類
・地窓
床面に接した足元にあるため、自然換気に効果的。
窓が取りにくい居室も地窓を設ければ風がよく通る。
・出窓
壁より外側に張り出した窓。開口部が大きいため室内が明るくなり、張り出し部分は飾り棚などに利用できる。
三角出窓、収納付き出窓などデザインも豊富。建ぺい率以上に屋内空間を確保する目的で採用することもある。
・天窓
屋根に取り付ける採光窓。天井部分からの採光は垂直な窓と比べ三倍の明るさを持つ。換気や通気のために開閉できるタイプもある。
・掃き出し窓
開口部が床面まであるタイプのもので、縁側をはじめ庭やテラスなどに面した場所に用いる。
掃除の際、昔はほうきで外に掃き出したのが由来で、別名テラス窓ともいう。
・ルーバー窓
数枚の定規のようなガラスを組み合わせた窓で、ジャロジー窓とも呼ばれている。
ハンドル操作で連動して動き、高い位置での換気も可能。目隠し効果もあるので、トイレ、浴室などにも利用される。
■間柱(まばしら)
本柱の間に立てる細い柱。建物にかかる荷重を負担するためでなく、壁を造るために取り付ける柱。
■無垢(むく)材
加工されていない木材のこと。
木材や石材などの純粋な単一材料を無垢といい、近年増えた加工品と単一材を区別するため使われるようになった。
塗装を施していない床材を呼ぶことが多いが、集成材や表面を張り合わせた化粧材などは無垢材には含まれない。
■メーターモジュール
一般住宅のモジュールとして、尺とメートルがあり、メーターモジュールは一㍍が基本寸法。
プレハブメーカーやハウスメーカーで広く採用されている。
部屋や廊下などの空間が尺モジュールより広くなるが、坪数を広げるか、同じ坪数で建てるならば間取りを調節しなければならない。
■免震構造
■メンテナンスフリー
建物や住まいの設備で、修理・点検などを施さなくても、その機能が損なわれないもの。
や行
■屋根の種類

屋根の形状により、
・切妻(きりづま)屋根
切妻(きりづま)屋根は、いわゆる「三角屋根」と呼ばれる屋根で、日本でも人気でよく取り入れられる形状。本を逆さまにしてかぶせたような形が特徴的。
・寄棟(よせむね)屋根
切妻屋根の妻側に屋根を足した四方に傾斜面がある屋根。頂点に棟があり、四方に面がある為、雨水を分散して流すことができる。耐風性が高く、外壁への負担も少ないことも寄棟屋根の特徴。
・片流れ(かたながれ)屋根
片流れ(かたながれ)屋根は、屋根面が一面で構成される屋根のことです。片方にだけ傾斜があり、シャープでデザイン性のある形状は近年人気が高まっている。面が大きい為、方角がよければソーラーパネルなどを効率よく運用できるといったメリットもある。
・陸屋根(りく・ろくやね)
陸屋根(りく・ろくやね)は、ビルの屋根のように平らな屋根のことです。モダンでスタイリッシュな現代的な雰囲気を演出でき、一般住宅でも取り入れられることの多い形状。屋上の利用には最適な屋根の形。勾配が小さいく水はけに難があるため、定期的な防水メンテナンスが必要となる。
・方形(ほうぎょう)屋根
方形(ほうぎょう)屋根とは、屋根の1か所が頂上になっている四角錐(ピラミッド型)の屋根です。寺院などに見られる六角形や八角形の建物の屋根も方形と呼ばれます。寄棟屋根に似ている形状で、同様のメリット・デメリットがあります。
・招き(まねき)屋根
招き(まねき)屋根とは、切妻屋根と片流れ屋根の間のような形状で、屋根の形が招き猫の前足に似ている為、そう呼ばれる。片方の屋根が短く、アシンメトリーな構造が特徴的。片流れ屋根と同様、採光性や通気性に優れ施工費もリーズナブルとメリットの多い形状。
・差し掛け(さしかけ)屋根
差し掛け(さしかけ)屋根とは、1階と2階の屋根が段違いになっている形の屋根。上記で紹介いたしました「招き屋根」も差し掛け屋根の一種であり、招き屋根と同様にメリットの多い屋根として近年人気が高まっている。屋根と屋根の間に外壁があるため、そこに窓を設置することができ、室内に光を取り入れたり、通気性を良くすることが可能。また、雨漏りのリスクがある為、入念な施工と定期的なメンテナンスが必要。
・入母屋(いりもや)屋根
入母屋(いりもや)屋根とは、寄棟屋根の上に小さな切妻屋根をかぶせたような屋根。和風作りの家によくみられる形で、日本瓦と相性が良く、複雑で重厚な形から格式の高い印象を感じさせてくれます。耐風性、断熱性に優れ、通気性も高いが、複雑な形状のため、建材が多く必要となり、コストが高い。
・半切妻(はんきりづま)屋根
半切妻(はんきりづま)屋根とは、切妻屋根の妻側の角に少し面を設けた屋根で、切妻屋根を途中から寄棟にしたような形状にも見える。建築基準法で高さ斜線制限などがある場合に利用されることがある。洋風のデザインの家によく用いられる屋根。
などがある。
■ユーティリティー
家事を行うスペース。
洗濯機を置いたり、アイロンなどを収納するカウンターを設けたりするなど、合理的に家事が行えるように工夫されている。
一般的にキッチンに接して造られる。
■床下換気口
木造住宅の布基礎部分に設ける小さい開口部のこと。
床下の風通しをよくし、湿気による木材の傷みや白アリ被害を防ぐ。
ら行
■ライトコート
建物の中央部に採光や風通しのために設けた吹き抜けスペース。
昔から京都の町屋などで、間口が狭く奥行きの長い建物の明かり取りや風通しをよくするために、坪庭や中庭を設けたのもその一例だ。
■ルーフバルコニー
階下の屋根の上を利用したバルコニーのことで、大きな面積を得ることができるため開放感が魅力。
防水施工技術が高まり、ガーデンスペースなどとしても活用できるようになっている。
■ロッキング現象
住宅などの建築物が地震で振動する時、軸組みは変形せずに、建築物全体が浮き上がる現象のこと。
特に構造用合板などで壁の強度を高めた「剛構造」の住宅などで多く発生する。
■LOW—Eガラス
表面に特殊な金属膜をコーティングしたガラス。
太陽の光は通すが、赤外線などは透過させないので、外光を取り入れ、室内の暖房の熱は逃がさない。
複層ガラスに使われることが多い。
わ行
■ワークトップ
キッチンの天板や作業台のこと。一部をカウンターとして使うことも多い。